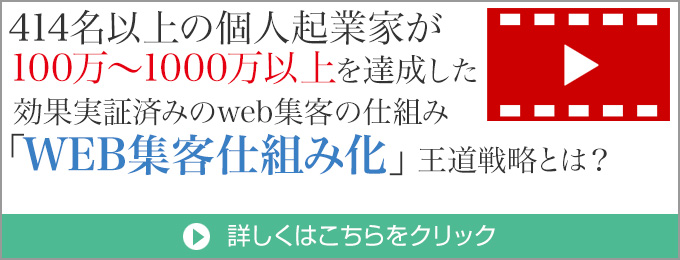どうも仙道です!
マーケティングやライティングの活動を行う際、様々な心理効果を使う機会があるはずです。その一つに「認知的不協和」というものがあります。
あまり聞き慣れないこの心理テクニックですが、実はキャッチフレーズに用いることで、絶大な効果を発揮するんです。
本記事では、認知的不協和音の概要や、具体的な活用方法について解説します。実際に集客と組み合わせたい場合は、以下の仙道塾でお伝えしている「web集客仕組み化」が役に立つので、ぜひ参考にしてください。
認知的不協和とは何か?
認知的不協和とは、ものごとに対し、個人が持つ認知と他との認知との間に発生する不一致、または不調和が生じることです。
ビジネスにおいては、その時に生じる不調和の解消または軽減しようする心の変化が用いられます。たとえば、今現在、あなたは集客ができていないとしましょう。そうすると、集客は難しいものという考え方、思考があなたの中に芽生えます。
ただ、他人から「集客は簡単だ」と言われると、そこに矛盾が発生しますよね。この矛盾を言い換えれば、集客は難しいという「現実」と、集客は簡単だという「情報」となります。
この時に起きる矛盾が不一致となり、不調和・不愉快感・違和感に変わります。これが認知的不協和となるのです。
認知的不協和はキャッチフレーズで使うのがおすすめ
認知的不協和は、先ほどの事例のようにキャッチフレーズとして使うのがおすすめです。
キャッチフレーズやキャッチコピーの役割は、読み手に興味を抱かせ、その先の文章などの中身を読ませる、見させることです。
読み手が一瞬で違和感を覚えられる矛盾を作り出すことができれば、それは反応の高いコピー(ランディングページやセールスレターなど)となります。
認知的不協和の使い方|マーケティングに効果的な事例
認知的不協和は、実は日常生活の中でも数多く使われています。使い方がわかればあなたのビジネスでも取り入れやすくなり、集客やセールスにおいて反応を高められるようになるでしょう。
認知的不協和の考え方
- 〇〇=△△(〇〇は△△である)という実態がある
- 〇〇=□□(〇〇は□□である)という知識・情報・結果がある
- □□と△△は矛盾する
上記のように考えることで、認知的不協和を作り出すことができます。
実際に使われている認知的不協和のキャッチフレーズ
- 偏差値が低いから東大には行けない
- 東大の偏差値は高い
- ダイエットは食事量を減らした方がよい
- ダイエットには食事を食べた方が良い
- ブラック企業には入りたくない
- 一般的に言われるブラック企業とは違う「成長するための」ブラック企業を定義
- CFOは若い人にはできない
- 18歳以下のCFOを対象にした募集を行う
これらは企業のキャッチフレーズとして使われているものですが、矛盾を作ることで違和感や矛盾への興味を作ることに成功しています。
読み手の中に矛盾を作り出すことで、読み手がそれを成正当化しようとする心理が働きます。正当化させることに対して、共感・否定・肯定などを行うことでより深く引き込むことができるでしょう。
認知的不協和は日常生活にも溢れている
日常生活における認知的不協和としては、たばこ・お酒・睡眠などを見るとわかりやすいと思います。
たばこのケース
事実:たばこを吸っている
矛盾:たばこは身体に悪い
お酒のケース
事実:お酒を毎日飲んでいる
矛盾:飲み過ぎは身体に悪い
睡眠のケース
事実:夜更かしが当たり前
矛盾:夜寝た方が身体に良い
その他に、次のようなケースも認知的不協和として成り立っています。
給料のケース
事実:給料を増やしたいが転職はできないと思っている
矛盾:未経験からでも転職ができる
旅行のケース
事実:ビジネスクラスに乗りたいが、その分旅先で美味しいものを食べたい
矛盾:ビジネスクラスに乗っている人は旅先でも美味しいものを食べている
こうした矛盾に気づくことができれば、認知的不協和を用いたキャッチフレーズも作りやすくなるでしょう。
まずは自分ごととして捉え、あなたがターゲットにする人が抱える事実と矛盾を見つけて、認知的不協和を上手く取り入れたコピーを作ってみてください。
認知的不協和音と合わせて読みたいマーケティングで使える心理効果
マーケティングに使える心理効果は、今回紹介した認知的不協和音だけではありません。本ブログでは、ダブルバインドやザイオンス効果、ゴルティロックス効果といった有用性の高いテクニックを多数解説しています。
上記を認知的不協和と合わせて使うことで、ここで紹介したキャッチフレーズだけではなく、ビジネス全体で顧客を動かすことができるようになるでしょう。
認知的不協和音でキャッチコピーの成果を高めよう
本記事では、心理効果における認知的不協和音の概要や、具体的な活用事例を解説してきました。
認知的不協和音は、人間の心に湧いてくる「矛盾」を逆手に取れる心理効果であり、人の目を惹くキャッチコピーの作成に役立ちます。そして、その他のテクニックと組み合わせることで、事業全体の成果を高めることができるので、ぜひ本記事を参考に適切な運用を心がけてみてください。